
共同の発展を求める
――中日両国は東アジア協力の中で更に広い空間を求め、そのうち金融面の協力、特にアジア元の構想はなおさら希望に満ちたものである。
中国国際問題研究所副研究員 姜躍春
中日関係は70年代のハネムーン期間と80年代の経済協力を主とする大発展の期間を経たあと、90年代から、協力と摩擦が共存する新しい段階に入った。30年来、中日両国が多くの段階、多くの分野、多くの問題の上で共通の認識に達したが、その中の最大の共通の認識は友好協力が両国の根本的利益に合致し、アジア太平洋地域の繁栄と安定に対し非常に重要な役割を果たすということである。中日関係発展の悠久な歴史も、和すれば双方に利益があり、闘えば双方とも傷がつくることを証明している。そのため、中日両国が国交正常化30周年を祝うにあたり、いかにして両国の間に現存する問題の解決方途を引き続き探求し、同時に努力して地域の事務あるいは多国間の分野で更に広範な協力の空間を求めることに努めるかは、両国が共に直面する重要な課題となるべきである。
しっかりした協力の基礎を備えた中日両国
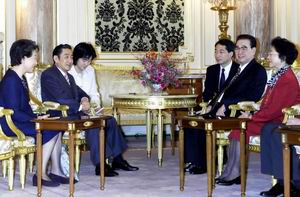 中日両国が国交正常化以来、政治関係が起伏したとはいえ、経済関係は東アジアの金融危機という外部の要素の衝撃を受けたほか、ほぼ持続的に上昇するという良好な勢いを維持している。これは経済発展段階における中日両国の違いと自然条件の差違が両国に経済協力の中で非常に大きな相互補完性を持せていることを物語っており、それより重要なのは良好な協力関係が両国の根本的利益に合致することを物語っていることである。
中日両国が国交正常化以来、政治関係が起伏したとはいえ、経済関係は東アジアの金融危機という外部の要素の衝撃を受けたほか、ほぼ持続的に上昇するという良好な勢いを維持している。これは経済発展段階における中日両国の違いと自然条件の差違が両国に経済協力の中で非常に大きな相互補完性を持せていることを物語っており、それより重要なのは良好な協力関係が両国の根本的利益に合致することを物語っていることである。
日本は長年続けて中国最大の貿易パートナーであり、1979年の中国の対日貿易総額は69億900万ドルしかなかったが、1981年に100億ドルを突破してからずっと上昇しつづけ、今年上半期の中日両国貿易額は450億ドルを突破して、451億ドルに達し、3年連続して上半期の最高貿易額を突破した。今年上半期の日本の世界貿易額は前年同期比7%減ったが、対中国輸出は逆に11%増え、同時に輸入額も前年同期とほぼ同じである。こうして、日本貿易総量に占める中日貿易のシェアは上昇し、前年同期より1.7%増えて、12.8%に達し、記録を更新した。中国はアメリカに継いて、日本の2番目の貿易国となった。
日本は一貫して中国の外資導入の主な供給国の1つである。80年代に、日本企業の対中国直接投資が相対的に少なかったとはいえ、中国の改革・開放の深化発展と中国市場に対する日本企業の理解の絶えまない深化に従い、90年代に入ってから、日本の対中国投資は大幅に増加し始め、1998年と1999年の2年はアジア金融危機の影響を受けたため2年連続して減少したほか、その他の年度はいずれも増加した。2000年末現在、日本企業の対中国直接投資プロジェクトは累計2万383社を上回り、実際に払い込んだ金額は278億100万ドルに達し、アメリカに次いで第二位にランクされている。2001年に西側の主要先進国に同時に経済低迷が現れた背景の下で、日本の対中国直接投資の契約ベース金額は54億2000万ドルに達し、前年より47.3%増え、実際に払い込んだ金額は43億5000万ドルで、前年より49%増えた。日本の対中国直接投資は増加が速く、払い込み率が高い特徴を呈しただけでなく、投資構造も以前の低附加価値部門から高附加価値部門に転換しつつある。
過去の30年間に、両国間の金融協力は長足の進展を遂げた。両国の中央銀行はハイレベルの相互訪問メカニズムを構築し、特に1997年のアジア金融危機の後、双方は各方面における交流と協力を強化し、アジア地域の安定と発展を守ることに貢献した。今年3月、中国は日本と通貨交換取決を結んだ。同取決は、中国の収支バランスがいったん重大に悪化すると、日本は中国に日本円を供給して、人民元と交換し、日本に同じ問題が現れるならば、中国は日本に人民元を供給して、日本円と交換すると規定している。そのほか、取決は日本中央銀行が中国人民銀行が市場に介入して襲撃を受けた人民元を保持する際に、日本円で人民元と交換することができるとも規定している。中国にとって、日本がタイに次ぐ2番目の取決締結国であり、世界外貨準備高の1、2位にある国の間に外国為替融通の安全保障体系を構築することは、両国の金融危機を防ぐ面の協力を新しい段階に上がらせただけでなく、同時にアジア地域の金融市場を安定させ、アジア太平洋地域諸国間の協力を促進する上でも重要な意義を持っている。
中日両国の効果的な協力は東アジア協力の無視できない重要な要素
 東アジア地域は欧米に比べて、地域化はひどく遅れているが、世界経済のグローバル化、地域経済の一体化が絶えず発展する今日の世界では、どのようにアジア太平洋地域の協力を強化し、日ましに激しくなる国際競争の中でアジア太平洋地域に有利な地位を失わせないようにするかは、当面の東アジア諸国にとっての緊迫課題である。戦後、東アジア諸国の経済が急速に発展し、60年代に日本経済がテイクオフし80年代に世界経済大国になったことに次いで、「アジアの4匹の竜」は70年代に、東南アジア諸国連合と中国は80年代に、経済成長にいずれも飛躍的な発展が現れた。現在、東アジアの人口は20億近く、世界人口の約3分の1を占め、人的資源が非常に豊富で、市場の潜在力が大きいが、各国の経済も一定の補完性があり、地域一体化を速める条件を備えている。
東アジア地域は欧米に比べて、地域化はひどく遅れているが、世界経済のグローバル化、地域経済の一体化が絶えず発展する今日の世界では、どのようにアジア太平洋地域の協力を強化し、日ましに激しくなる国際競争の中でアジア太平洋地域に有利な地位を失わせないようにするかは、当面の東アジア諸国にとっての緊迫課題である。戦後、東アジア諸国の経済が急速に発展し、60年代に日本経済がテイクオフし80年代に世界経済大国になったことに次いで、「アジアの4匹の竜」は70年代に、東南アジア諸国連合と中国は80年代に、経済成長にいずれも飛躍的な発展が現れた。現在、東アジアの人口は20億近く、世界人口の約3分の1を占め、人的資源が非常に豊富で、市場の潜在力が大きいが、各国の経済も一定の補完性があり、地域一体化を速める条件を備えている。
日本は全般的な経済実力が世界第2位にランクされている経済強国であり、制造業の実力が世界の上位にランクされる国でもあり、中国は世界で経済発展が最も速い国であり、市場の潜在力が最も大きな国でもあり、中日両国の2001年のGDPは6兆ドルに近く、外貨準備高は7000万ドル以上であり、東アジアでも世界でも1、2位に数えられる国であり、国際競争がますます激しくなり、技術イノベーションと市場ニーズも日に日に重要になる今日の世界においては、産業分業、需給関係および所在地域における両国の独特な地位は、両国が今後の東アジア協力の中でかならず重要な役割を発揮することを決定づけている。日本と中国を問わず、もし欧米の経済圏と単独に闘うならば、必ず失敗する。東アジア経済圏は未来の経済競争の中で不敗の地に立ちたいならば、かなり程度において中日間の効果的な協力によって決定づけられる。
 東アジア金融危機が終わってからすでに数年にたつが、金融のグローバル化と情報技術革命が地域の経済発展にもたらしたショックとプレッシャーは軽減せず、その上東アジア諸国の改革の進度もアンバランスである。そのため、金融リスクを防ぎ、金融秩序を安定させ、経済安全を守るのは、依然として今後数年に東アジア諸国が直面する最も重要な任務である。金融分野における東アジア地域の協力はすでによいスタートが現れたが、世界のその他の地域と比べてやはり始動の段階にある。東アジア金融危機の現実は、中日両国が金融分野改革という共通の需要に直面していることを物語っている。通貨相互交換取決の調印はなおさら中日両国が金融分野で協力を深める条件と可能性があることを物語っている。ユーロがスタートしてから、東アジア諸国の学者と通貨当局はすでに未来のアジア太平洋地域の通貨の発展趨勢についていろいろな研究を行い、構想を打ち出し始めたが、日本政府のシンクタンクはかつて多種の通貨からなる「一括通貨制度」および日本円と人民元が共同で構成するアジア元構想を打ち出した。これらの構想がアジア太平洋地域協力の実際の進展にとって時期尚早であるが、経済のグローバル化と地域化進展の発展趨勢から見て、この地域が考え始めなければならない課題である。中日両国は学術界でこれらの問題の系統的分析と科学的論証を始めるべきであり、自国政府の関係部門に研究成果に定期的に提出して、東アジアの通貨協力の絶えまない深化発展を促進すべきである。
東アジア金融危機が終わってからすでに数年にたつが、金融のグローバル化と情報技術革命が地域の経済発展にもたらしたショックとプレッシャーは軽減せず、その上東アジア諸国の改革の進度もアンバランスである。そのため、金融リスクを防ぎ、金融秩序を安定させ、経済安全を守るのは、依然として今後数年に東アジア諸国が直面する最も重要な任務である。金融分野における東アジア地域の協力はすでによいスタートが現れたが、世界のその他の地域と比べてやはり始動の段階にある。東アジア金融危機の現実は、中日両国が金融分野改革という共通の需要に直面していることを物語っている。通貨相互交換取決の調印はなおさら中日両国が金融分野で協力を深める条件と可能性があることを物語っている。ユーロがスタートしてから、東アジア諸国の学者と通貨当局はすでに未来のアジア太平洋地域の通貨の発展趨勢についていろいろな研究を行い、構想を打ち出し始めたが、日本政府のシンクタンクはかつて多種の通貨からなる「一括通貨制度」および日本円と人民元が共同で構成するアジア元構想を打ち出した。これらの構想がアジア太平洋地域協力の実際の進展にとって時期尚早であるが、経済のグローバル化と地域化進展の発展趨勢から見て、この地域が考え始めなければならない課題である。中日両国は学術界でこれらの問題の系統的分析と科学的論証を始めるべきであり、自国政府の関係部門に研究成果に定期的に提出して、東アジアの通貨協力の絶えまない深化発展を促進すべきである。
自由貿易区設置は東アジア協力の中期目標となるべきである。貿易投資自由化の促進はすでにアジア太平洋地域諸国の共通の認識となっており、APECの今年の発展はすでにアジア太平洋地域の貿易投資自由化のために全般的なタイムテーブルを確立した。東アジア地域はアジア太平洋地域と比べて自由貿易区を設置する必要と可能性がいっそうあり、各国は積極的に10+3の枠組み内で自由貿易区設置を東アジア地域協力を推進する中長期の目標とすべきである。ここ数年、経済グローバル化の進展に従って、地域経済一体化が絶えず加速している。ヨーロッパ経済一体化のレベルは最高で、関税同盟もあれば統一通貨もあり、協力の地域はすでに以前の12カ国から18カ国に拡大され、今後東への拡大が予想されている。北米自由貿易協定(NAFTA)は中南米に向かって広げつつあり、2005年にアメリカ自由貿易協定(FTAA)を締結することを計画している。南アジア、中東、アフリカもいずれもそれぞれ形の異なる地域経済貿易組織がある。ここ数年、これらの地域貿易組織は域外諸国の製品に障害を設け、東アジア諸国の対外貿易の正常な発展を制約した。80年代末に入ってから、域内貿易はすでに著しい発展をとげ、日本と東南アジア諸国連合、中国の間の相互貿易額はすでに自国の対外貿易総額の中で重要な地位を占めている。現在、東アジアでは、東南アジア諸国連合諸国が貿易自由化の推進を積極的に加速するほか、日本とシンガポール、韓国はすでに二国間の自由貿易協定締結について討論を始めた。中国と東南アジア諸国連合、日本と東南アジア諸国連合の間も自由貿易を加速する面で目に見える進展をとげた。地域全体の自由貿易区の進展のカギは中日両国の政策にある。