互恵の経済関係
――中米両国は経済分野で互恵協力を展開しており、貿易摩擦が協力の主流に影響を及ぼすことがあってはならない。
周世儉
(中華米国学会常務理事会理事)
王麗軍
(首都経済貿易大学副教授)
胡錦濤国家主席は米国を公式訪問し、20日にブッシュ大統領と会談する。重要議題の1つは経済貿易関係である。中米関係では経済貿易面での協力が重要な一部になっているからだ。
 今世紀に入り、中米間の経済貿易協力は急速に発展し、互恵の関係は順調に推移している。中国通関統計によると、2000年の対米輸出額は521億ドルだったが、2005年に217.7%増の1629億ドルに達した。米国通関統計によると、2000年の対中輸出額は162億ドル、2005年には157.5%増えて418億ドルとなった。米国の15大貿易パートナーの中で、対中輸出が伸び率、伸び幅ともに最も高い。 今世紀に入り、中米間の経済貿易協力は急速に発展し、互恵の関係は順調に推移している。中国通関統計によると、2000年の対米輸出額は521億ドルだったが、2005年に217.7%増の1629億ドルに達した。米国通関統計によると、2000年の対中輸出額は162億ドル、2005年には157.5%増えて418億ドルとなった。米国の15大貿易パートナーの中で、対中輸出が伸び率、伸び幅ともに最も高い。
米国側の統計で、中国は2004年に第4の貿易パートナーとなった。輸入は4位、輸出は11位。2005年に第3位となり、輸入は2位、輸出は4位。カナダ、メキシコ、日本に次いで米国の重要な貿易パートナーとなった。ブッシュ大統領が3月9日に表明したように、中国は米国の貿易にとって戦略的パートナーなのである。中国側の統計では、2005年の対米輸出額は1629億ドルに達し、米国の輸入総額1兆6714億ドルの9.75%、米国からの輸入額は487億ドルで、米国の輸出総額9043億ドルの5.4%を占めた。実際に国別に見ると、中国にとって米国は最大の貿易パートナーであり、最大の海外市場でもある。対米輸出額は輸出総額の21.4%を占めた。
米国側統計では、中国の2005年の輸出額は2435億ドルに達し、中国の輸出総額7620億ドルの32%、米国の輸入総額の14.6%を占めた。この数字が示すように、中米両国は互いに大市場となっている。米商務省は1994年、中国を世界10大新興市場のトップにすると表明しているが、この十数年来の事実でこれが立証された形だ。
商品と同様、資本も市場が必要であり、比較的高い利益が失われれば、資本も萎縮する。統計によると、2005年末現在、米国の対中投資額は511億ドルに達した。中国が米国資本にとって海外の新興大市場であり、海外の重要なパートナーであることを物語る数字だ。中国は西欧、北米、中南米、日本の次ぐ位置にある。
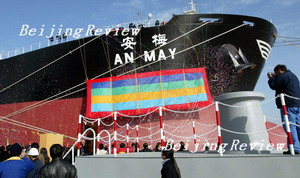 中米両国は金融分野の協力でも顕著な成果を上げている。2005年11月末現在、中国は2544億ドルの米国債を保有しており、このほか米企業株や個人債券もかなりの額にのぼる。2005年末に外貨準備高は8000億ドルを突破したが、その約60%は米国資産だ。 中米両国は金融分野の協力でも顕著な成果を上げている。2005年11月末現在、中国は2544億ドルの米国債を保有しており、このほか米企業株や個人債券もかなりの額にのぼる。2005年末に外貨準備高は8000億ドルを突破したが、その約60%は米国資産だ。
2005年初め以来、中米両国の経済貿易関係は総体的に比較的安定した状態と順調な発展傾向を維持してきたが、多事の秋を迎えると、衝突や摩擦が目立って増大するようになった。今後数年内に、中米は経済貿易面で、知的財産権の保護や人民元レート、貿易の均衡、繊維製品といった問題やサービス業の相互開放など、大きな注目される問題に直面するだろう。
長年にわたり、中米間の貿易摩擦は両国それぞれの側で絶えず起きていたが、それは国家間の根本的な利害衝突ではなく、両国の一部産業界との間の経済的利益をめぐる矛盾が大半であるため、平等な話し合いを通じて互いに理解し譲歩すれば解決されると見るべきだ。このことは長年の経験がはっきりと物語っている。しかも、こうした摩擦は中米の経済貿易関係では主流ではなく、経済貿易協力という主流に影響を及ぼすことがあってはならない。摩擦や紛争が生じた場合、双方がより高い視点を持ち、より広い視野を持つのは当然であり、全局に立って慎重に処理することで、矛盾が深まるのを防がなければならない。
平等互恵は経済貿易協力を展開するための基本的前提であり、優位性の相互補完は経済貿易協力を拡大するための重要な条件であり、友好的な話し合いは紛争を処理するための有効な方法である。なにかと制裁や報復をもって脅威を与えるやり方は講じるべきではない。多国間貿易メカニズムの原則に背くだけでなく、問題の解決には役立たず、問題を複雑化、深刻化させるだけだ。貿易戦争の結果、双方はともに傷つくだけであり、誰もメリットは得られず、さらに中米の二国間貿易と関係が緊密な国・地域に損害を与えることにもなり、他国に居ながらにして“漁夫の利”を占めさせるだけである。そのため人心を得られるものではなく、自国の広範な経済人の支持を得ることもできない。このことは、繊維製品をめぐって緊急輸入制限措置(セーフガード)を発動し、それに対抗してさらにセーフガード発動する、といった2005年に中米両国で起きた争いを見ればはっきりと分かる。2005年6月17日から11月8日まで、両国の政府代表団は7回にわたって困難な交渉を臨み、ようやく「繊維製品と衣料品の貿易に関する覚書き」に調印した。この覚書きは、相互理解と譲歩、互恵の協力精神を体現しており、経済貿易分野でのその他の摩擦や紛争を解決する上でも理想とするモデルとなるものであり、安定した繊維製品の貿易環境の整備、経済貿易協力のさらなる発展の促進に役立つものだ。
 現在、経済貿易関係で比較的突出した問題は、米国の対中貿易赤字問題である。中国通関統計によると、2005年の対米貿易黒字は1142億だが、米国商務省統計では、対中貿易赤字は2016億ドルに達している。 現在、経済貿易関係で比較的突出した問題は、米国の対中貿易赤字問題である。中国通関統計によると、2005年の対米貿易黒字は1142億だが、米国商務省統計では、対中貿易赤字は2016億ドルに達している。
米国が中国から輸入する大量の高品質低価格の日用消費品は米国市場のニーズに合っており、広大な消費者にプラスとなり、米国のインフレ緩和に役立ち、米国の産業構造の調整と米国経済の発展にとって有利である。赤字は一種の貿易に伴う行為であり、市場のニーズから分析、観察すべきだ。中国は米国に4、5000万の靴を輸出してはじめてボーイング747大型旅客機と交換できるからといって、労働集約型日用商品を大量に輸出することで少量のハイテク設備と技術を交換する発展途上国は貿易で優位にある、と簡単に認定することはできない。中米両国の経済貿易協力では、米国側に優位にある。1993年から始まった米国の対中貿易赤字は主に、米国が持つハイテクという優位性がまだ発揮されていないためだ。ハイテクの輸出規制を緩めることが、対中貿易赤字を緩和、減少させる近道である。赤字緩和の主動権は米国が握っているのである。
米国の貿易赤字は経済のグローバル化と国際産業構造調整の必然の結果であり、大規模かつ最も広範な国際分業の必然の産物でもある。米国の貿易赤字は構造的なものであり、逆転するのは難しい。
中米貿易の不均衡問題をいかに見るべきか。
先ず、対米輸出では加工貿易がおよそ70%と、非常に大きな比重を占めているのが中米貿易の1つの主要な特徴だ。これは、中国はわずかな加工費しか得られないことを意味する。米国市場で人気のバビー人形を例に見ると、販売価格は9.99ドルだが、中国からの輸入価格は2ドルに過ぎない。うち原材料は中東から輸入しており、さらに台湾で半製品に加工され、髪は日本が生産し、包装材料は米国が提供し、この3プロセスで合計1ドルかかる。さらに輸送・管理費が0.65ドルと、中国が得る加工費はわずか0.35ドルに過ぎない。原産地ルールに基づき、この2ドルはすべて中国の対米輸出額として統計されるが、これでは両国間の実際の貿易状況が正確に反映されないのは明らかだ。こうした伝統的な貿易統計方法では、当今の中米貿易の不均衡問題は説明できないと指摘しておく必要がある。
 次に、中国が導入する外資の70%は東アジアによるものだ。長年にわたり日本や韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピンなどの国・地域がもともと貿易黒字だった製品を中国大陸にシフトしたことで、「貿易均衡移転反応」が生じた。そのため、こうした「三資企業」(合弁・合作・単独出資)の製品(大半の部品・パーツは上述した国・地域から輸入)は「Made
in China」ではなく「Made in Asia」であり、米国から得られる貿易黒字は上述国・地域が分かち合っており、中国だけが得るものではない。米国通関統計によると、2000年の上述国・地域からの輸入額は3023億ドルだったが、2005年になると輸入は増えず、逆に2.5%減って2947億ドルとなった。同年の中国からの輸入額は1000億ドルから一気に2435億ドルと、143%も急増している。中国通関統計によると、2005年の対米貿易黒字は1142億ドルだが、上述国・地域に対しては1400億ドルの赤字となった。この意味から言えば、中国はアジアの1つの加工センターである。国家統計局の李徳水局長が指摘するように、「中国の米欧に対する巨額の黒字は実際には行きずりの神の福」であり、見かけ倒しのものなのだ。 次に、中国が導入する外資の70%は東アジアによるものだ。長年にわたり日本や韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピンなどの国・地域がもともと貿易黒字だった製品を中国大陸にシフトしたことで、「貿易均衡移転反応」が生じた。そのため、こうした「三資企業」(合弁・合作・単独出資)の製品(大半の部品・パーツは上述した国・地域から輸入)は「Made
in China」ではなく「Made in Asia」であり、米国から得られる貿易黒字は上述国・地域が分かち合っており、中国だけが得るものではない。米国通関統計によると、2000年の上述国・地域からの輸入額は3023億ドルだったが、2005年になると輸入は増えず、逆に2.5%減って2947億ドルとなった。同年の中国からの輸入額は1000億ドルから一気に2435億ドルと、143%も急増している。中国通関統計によると、2005年の対米貿易黒字は1142億ドルだが、上述国・地域に対しては1400億ドルの赤字となった。この意味から言えば、中国はアジアの1つの加工センターである。国家統計局の李徳水局長が指摘するように、「中国の米欧に対する巨額の黒字は実際には行きずりの神の福」であり、見かけ倒しのものなのだ。
第3に、中米両国は経済貿易では商品貿易、技術貿易、サービス貿易、相互投資の4分野で関係が強い。通常言われる外資の赤字とは、商品貿易の赤字を指す。米国は対中経済貿易ではまさに後者の3つの分野で優位にある。2005年末現在、米国企業の実際投資額は511億ドル、設立した企業数は4万9000社にのぼる。これら企業が生産する製品の大半は中国市場で販売されており、米国市場への逆輸出は一部を占めるに過ぎない。ゼネラル・モーターズとモトローラを例にすると、同社が中国で生産する自動車と携帯電話のニーズは旺盛であり、すでに実際には中国が米国から輸入する同製品に取って代わる存在となっている。米資本企業は中国で得た利益を投資の拡大に回しているほか、一部は米国に送金しており、実際には対中貿易赤字の一部は埋められている。中国商務部の暫定統計によると、米資本企業の2004年の中国での販売額は750億ドルに達した。その年の対中貿易赤字1620億ドルの46%を埋められる数字だ。
2001年〜2005年の5年間で、中国の輸入総額は2兆1731億ドルに達したが、2006年〜2010年には4兆ドルが見込まれる。これは本物の新興大市場である。ブッシュ政権がリーガン政権のやり方にならって、対中輸出規制を大幅に緩めれば、米国の大・中堅企業は能力を持てるようになり、中国というこの急成長する新興大市場でより多くのシェアを占める可能性もあり、中国は必ず米国にとって輸出の大市場となるだろう。中米両国は産業構造上、強い相互補完性を有しているが、経済貿易協力が必然的に幅の広い将来性のあるものとなるか、必然的にさらなる発展を遂げるかは、これによって左右される。米国の資金と技術、管理ノウハウ、それに中国の巨大な市場と廉価な労働力資源を結合させれば、両国の経済には必ず発展に向けた巨額の利益がもたらされ、両国の経済振興に大いに役立つはずだ。中国は近代化の実現という壮大な過程で米国の資金と技術・設備を大量に必要としており、これも米国経済の発展をけん引し、促進することだろう。そのため、中米の経済貿易協力は互恵の、双方がともに利益を得られるものであり、その将来性は非常に幅の広いものだと言える。27年以来の中国の改革・開放と近代化による最大の受益者はもちろん中国人民であり、海外で最大の受益者は米国と日本である。
|