| 人類は大自然を畏敬すべきか
2004年末、インド洋沿岸諸国を突如襲った大津波で一瞬にして約23万人が犠牲となった。
 これは全地球的な災害であり、人類共通の災難でもある。人類が大自然を征服するとの自信は、この災難によって揺るがされたとの声がある。何故なら、今回の大津波から、人類はいかに小さな存在で脆弱であり、地球環境のどんなに微小で突然的な変化であれ、我々に壊滅的な災害がもたらされるが、人類はそうした災害を防ぐことができない、ということを感じとったからだ。こうしたことから、人類自身の能力に疑問を抱き、今回の災難は我々に、自然を予め察知できる対象、または「打ち勝つ」ことのできる相手にするのではなく、自然の前では謙虚で畏敬の念を持たなければならない、と警鐘を鳴らしているとの声も聞かれる。 これは全地球的な災害であり、人類共通の災難でもある。人類が大自然を征服するとの自信は、この災難によって揺るがされたとの声がある。何故なら、今回の大津波から、人類はいかに小さな存在で脆弱であり、地球環境のどんなに微小で突然的な変化であれ、我々に壊滅的な災害がもたらされるが、人類はそうした災害を防ぐことができない、ということを感じとったからだ。こうしたことから、人類自身の能力に疑問を抱き、今回の災難は我々に、自然を予め察知できる対象、または「打ち勝つ」ことのできる相手にするのではなく、自然の前では謙虚で畏敬の念を持たなければならない、と警鐘を鳴らしているとの声も聞かれる。
だが、「科学技術の急速な発展に伴い、人類自身の能力と、自然を開発し自然を征服する能力は過去例を見ないまでに強化された。従って、人類が大自然を畏敬する必要はなく、逆に、大自然に対し尽くせることは尽くすべきだ」、というのが多くの人の考えだ。
人と自然との関係は長年、専門家たちが関心を寄せる問題となってきた。今回のインド洋の大津波を契機に、人類と大自然の運命に関心を持つ多くの人たちの間で大きな論議が巻き起こっている。人と自然では、どちらを本と為すべきか。大自然の畏敬は反科学的ではないか。人類は大自然を畏敬すべきか。人と自然の関係をいかに処理するかなど……。
人と自然では、どちらを本と為すのか
◆人を本と為すべきである
 中国科学院会員で理論物理学者・何袮?氏――インド洋の大地震と津波は人類に最高の教訓を与えてくれた。人と自然との関係において、我々はその認識を深めることが大切だということだ。天と人との間の不完全さは、言えば調和された一側面であり、また非調和的な一側面でもあることを人類は看取しなければならない。この関係を冷静に判断しなければ、警戒を怠ることになり、災害という重大な結果がもたらされることになる。 中国科学院会員で理論物理学者・何袮?氏――インド洋の大地震と津波は人類に最高の教訓を与えてくれた。人と自然との関係において、我々はその認識を深めることが大切だということだ。天と人との間の不完全さは、言えば調和された一側面であり、また非調和的な一側面でもあることを人類は看取しなければならない。この関係を冷静に判断しなければ、警戒を怠ることになり、災害という重大な結果がもたらされることになる。
歴史的に言えば、人類が発展し始めた当初、人類の自然に対する抵抗力は有限であった。そうしたことから、一部の進歩的な思想家は人が天に勝つことを強調し、人類と自然界との闘争を鼓舞した。科学技術が発展するに伴ってこの数年来、人類の能力は益々高まってきた。あたかも自然界の多くの問題は、人類が解決できるかのごとく。そのため現在、人類による行き過ぎた自然界の破壊、それはむしろ人類にマイナスになると恐れることから、調和が必要だと強調する声が一部で聞かれる。
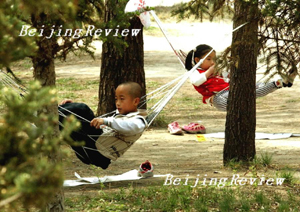 多くの環境・生態学者が市民に対し環境や生態の保護に注意を払うよう呼びかけているが、これは理にかなったものだ。この数年来、人類の生産力が急速に発展してきたため、確かに一部で環境や生態が不必要に破壊されている。だが更に言いたいのは、我々一部の環境・生態学者の間に偏った見方があることだ。つまり、環境と生態は変えてはならないという考え方で、全ての「大自然の改造」という主張はこうした学者たちの反対に遭遇している。だが、こうした見方は人類の利益には合致しない。 多くの環境・生態学者が市民に対し環境や生態の保護に注意を払うよう呼びかけているが、これは理にかなったものだ。この数年来、人類の生産力が急速に発展してきたため、確かに一部で環境や生態が不必要に破壊されている。だが更に言いたいのは、我々一部の環境・生態学者の間に偏った見方があることだ。つまり、環境と生態は変えてはならないという考え方で、全ての「大自然の改造」という主張はこうした学者たちの反対に遭遇している。だが、こうした見方は人類の利益には合致しない。
この問題は明確にさせなければならない。何故なら、実際的な仕事に影響を及ぼすからだ。現在、中国では電力不足の状態にある。水エネルギーを開発し、ダムを建設しなければならないが、そうすれば、一部で環境や生態が破壊されることは避けられない。そこには利害得失の問題がある。仮に、環境や生態の保護が過度に強調されれば、ダムを建設することは不可能となる。こうした状況に遭遇した場合、利害の軽重や得失を判断するに当たり、人をもって本と為す、を基準とすべきだと考える。胡錦涛総書記は『科学的発展観を樹立し着実に実施する』との演説の中で、環境事業については科学的発展観をもって幾つかの点を理解するよう指導すると指摘している。そのうちの1点が、「人を本と為すとの考え方を確実に樹立する」というものだ。
◆自然を本と為すことこそが、真に人を本と為すである
北京の学者・付涛氏――人類は大自然に依存してこそ生きられるのであり、それが無くなれば人類生存の基盤は失われてしまう。自然を本と為すことこそが、真に人を本と為すことである。自然を平等に尊重せず、自然と生態を少しも顧みない「人を本と為す」との考えの本質は、したいことをするという人類中心主義にほかならない。大自然を畏敬し続け、伝統的な知識や文化遺産を尊重することは、生態保護にとって独特の価値を有することであり、勢いを増す科学が理性を失わず、誤った道に陥らないよう保証するものでもある。何会員が言う「人を本と為す」との理念は、まさにその中に内包される民本思想と公平な考え方から離脱しており、この理念の本質が軽視されている。
 雲南省に3本の河川が合流する地帯がある。ここには22の民族が居住している。彼らは共同で多様的な文化と宗教を融合させる試みに取り組み、有限の資源を長期にわたり調和的に共存させてきた。実際、今日でも、我々が擁する多くの既に縁に追いやられ、非主流となり、ひいては科学や現代工業文明から“嘲笑”されている文化遺産の中にも、人類が自己の知恵をもって自然を畏敬し、自然と調和を取りながら共存してきたケースを見て取ることができる。例えばインド洋の大津波だ。タイの新聞が報じていたが、ある村の65歳の村長が海水の引いていくのを見た時に、以前に年配者が語っていた言葉を思い出した。「海水が急速に引いたら、同量の海水が勢いを増して巻き上がって来る」。そこで村長は181人の村民を山の上に避難させ、運良く村民を難から救ったという内容の記事だ。この例でも分かるように、人間は決して科学に依存するのではなく、自然と共存する知恵に依存することで生きる方法を身に付け、危険から免れることができるのだ。こうした非科学的であっても、実際に経験して、文化として蓄積されるものこそが、人類の貴重な生きる知恵の源となる。 雲南省に3本の河川が合流する地帯がある。ここには22の民族が居住している。彼らは共同で多様的な文化と宗教を融合させる試みに取り組み、有限の資源を長期にわたり調和的に共存させてきた。実際、今日でも、我々が擁する多くの既に縁に追いやられ、非主流となり、ひいては科学や現代工業文明から“嘲笑”されている文化遺産の中にも、人類が自己の知恵をもって自然を畏敬し、自然と調和を取りながら共存してきたケースを見て取ることができる。例えばインド洋の大津波だ。タイの新聞が報じていたが、ある村の65歳の村長が海水の引いていくのを見た時に、以前に年配者が語っていた言葉を思い出した。「海水が急速に引いたら、同量の海水が勢いを増して巻き上がって来る」。そこで村長は181人の村民を山の上に避難させ、運良く村民を難から救ったという内容の記事だ。この例でも分かるように、人間は決して科学に依存するのではなく、自然と共存する知恵に依存することで生きる方法を身に付け、危険から免れることができるのだ。こうした非科学的であっても、実際に経験して、文化として蓄積されるものこそが、人類の貴重な生きる知恵の源となる。
何会員が言う人と自然を単純的に対立させた見方は、まさに環境と人類の共通性の一面を無理に切り裂くものであり、それを征服と被征服の関係に置き換えようとするものである。事実が証明するように、科学は両刃の剣だ。人類の自然を征服する能力が強くなれば、それだけ自然を破壊する能力もまた強くなっていく。自然の征服とは実際、幼児期の憧憬に見られる一種の幼稚的な幻想であり、既に成熟期に入った人類は先賢の知恵と文化からその精髄を汲み取り、自ら成熟した広い気持ちを持つよう心がけて、自身と自然との関係を理性的な眼で見つめるべきだ。
◆大自然を畏敬する必要はない、というのは妄言である
 北京の環境保護提唱者・楊斌氏――人類史を見ると、不可抗力な天災に遭遇するたびに決まって、為すすべも無いと感じる人や、人類自身の能力に疑問を抱く人、大自然を畏敬する気持ちを抱く人がいる。実際、人類が為すすべが無いと感じるのは、決して天災そのものが原因ではなく、天災発生の要因やその運動メカニズムに対する認識に限界を感じているのが主因だ。全ての学者、殊に自然科学の研究に従事している学者の間において、未知の世界に向かい合い、それを解決できなかった時に、為すすべが無いのは仕方がないと感じる、それはざらにあることだ。よしんば成果を上げた自然科学の研究者であっても、その理論が後世の者によって補完され、或いは更に研究が進んで覆された場合、より深層的な為すすべの無さを感じて、未知の世界に対し畏敬の念が生じることもある。 北京の環境保護提唱者・楊斌氏――人類史を見ると、不可抗力な天災に遭遇するたびに決まって、為すすべも無いと感じる人や、人類自身の能力に疑問を抱く人、大自然を畏敬する気持ちを抱く人がいる。実際、人類が為すすべが無いと感じるのは、決して天災そのものが原因ではなく、天災発生の要因やその運動メカニズムに対する認識に限界を感じているのが主因だ。全ての学者、殊に自然科学の研究に従事している学者の間において、未知の世界に向かい合い、それを解決できなかった時に、為すすべが無いのは仕方がないと感じる、それはざらにあることだ。よしんば成果を上げた自然科学の研究者であっても、その理論が後世の者によって補完され、或いは更に研究が進んで覆された場合、より深層的な為すすべの無さを感じて、未知の世界に対し畏敬の念が生じることもある。
人類の現代科学の歴史は400年に過ぎず、この400年の間に絶えず新たな仮設が、新たな学科が生まれてきた。極めて急速に発展する科学は絶えず更新され、従来の理論は淘汰されていく。たとえそうであれ、我々が宇宙に向かい合い、依存して生きる生態システムや我々そのものに正面から向かい合った場合、例えば我々の大脳はどうだろうか、やはり為すすべを無くすだろう。科学という大きな旗をむやみに且つ尊大に掲げ、自然を征服し、自然を改造する、とのスローガン吹聴しながら行う愚昧な行動がいかに多いことか。
人と自然の関係をいかに処理するか
◆人類は自然災害に対し為すべきことを
 中国科学院会員で理論物理学者・何袮?氏――今回の津波は人類にいま1つの啓示を与えてくれた。人類は自然災害に対し為すべきことが無いのではなく、為すべきことがある、ということだ。 中国科学院会員で理論物理学者・何袮?氏――今回の津波は人類にいま1つの啓示を与えてくれた。人類は自然災害に対し為すべきことが無いのではなく、為すべきことがある、ということだ。
現在のところ、人類の自然の規律に対する認識はまだ始まった段階に過ぎない。今回の津波が予見できなかったことは非常に遺憾であり、これは科学的水準の問題だ。はっきり言えば、人類が地震を予測する根拠にしているものは決して確実であるとは言えない。地震による津波が発生するという段階になってようやく、警戒態勢が取れるのが現状だ。現在では、人類が自然災害の発生を未然に防ぐことは不可能ではあるが、警戒に向けた準備は整えることができる。地震による津波に対しては、防御がカギとなる。家屋の耐震性を高めることが予想することより先ず重要である。耐震性の強化は確実に実行できるからだ。
北京市民・柯南氏――確かに、一部の水利施設には失敗したものもあるが、一部では成功したものがあるものも確かだ。例えば、「自然は少しも改変されてはならない」との基準に基づけば、どんな水利施設もない、というのが成功したものとなるだろう。だが、この基準に沿って言えば、人類は最初から環境にとっては脅威であり、最も原始的な農業ですら、自然への背反となる。
だが、どの生物もこの自然の規律が進化された支配の下で生き続けてきたのであり、彼らは常に環境を変えている。
「大自然を畏敬する」との考え方は捨て去り、より建設的な観点から我々が置かれている環境に対処することが、我々の環境と我々の未来を保護する第1歩になると考える。
◆自然を単に人類の工具と見なすことはできない
 北京の環境保護ボランティア・梁従誠氏――環境倫理学界が一貫して関心を寄せている理論の焦点となるのは、自然の価値ということだ。いかなる人も、人は自然の産物であり、大自然は人類の母である、ということは否定できないと考える。では、これまで人類と地球上の様々な生命を育んできた大自然は、単に工具としての価値しかないのか、それとも、自然自身の内在的な価値を有しているのか。人類は畢竟、動物とは異なり、動物にとって、自然界は2つの物しか存在していない。食べられる物か、食べられない物かであり、その他はいわゆる価値など無いのだ。自然に対する価値判断に言えば、単純に自然を生き続けるための依拠と見なす考え方から脱却して初めて、人類はより次元の高い理性的な思考を持てるのである。仮に人類が自分の生母は工具的な価値しかないと考えた場合、それは母親に対する汚辱であり、また自身に対する汚辱でもあり、同様の道理からして、それは大自然という人類共通の母親にもかかわることでもある。実際に、人類は、殊に我々中国人は早くから大自然に工具を超える価値を与えてきたのであり、中国古代の数多くの哲学や文芸作品はいずれも、自然の美しさとそこから感じ取る倫理や原則をテーマとしてきた。老子の『道徳経』にある「人は地に従い、地は天に従い、天は道に従い、道は自然に従う」というのは、まさにこの道理を示している。中国古代の文人は、自然は美しいばかりでなく、「徳」をも備えていると考えていた。自然を人類の「工具」に過ぎないと見なすのは、歴史上、中国哲学の伝統ではないのだ。 北京の環境保護ボランティア・梁従誠氏――環境倫理学界が一貫して関心を寄せている理論の焦点となるのは、自然の価値ということだ。いかなる人も、人は自然の産物であり、大自然は人類の母である、ということは否定できないと考える。では、これまで人類と地球上の様々な生命を育んできた大自然は、単に工具としての価値しかないのか、それとも、自然自身の内在的な価値を有しているのか。人類は畢竟、動物とは異なり、動物にとって、自然界は2つの物しか存在していない。食べられる物か、食べられない物かであり、その他はいわゆる価値など無いのだ。自然に対する価値判断に言えば、単純に自然を生き続けるための依拠と見なす考え方から脱却して初めて、人類はより次元の高い理性的な思考を持てるのである。仮に人類が自分の生母は工具的な価値しかないと考えた場合、それは母親に対する汚辱であり、また自身に対する汚辱でもあり、同様の道理からして、それは大自然という人類共通の母親にもかかわることでもある。実際に、人類は、殊に我々中国人は早くから大自然に工具を超える価値を与えてきたのであり、中国古代の数多くの哲学や文芸作品はいずれも、自然の美しさとそこから感じ取る倫理や原則をテーマとしてきた。老子の『道徳経』にある「人は地に従い、地は天に従い、天は道に従い、道は自然に従う」というのは、まさにこの道理を示している。中国古代の文人は、自然は美しいばかりでなく、「徳」をも備えていると考えていた。自然を人類の「工具」に過ぎないと見なすのは、歴史上、中国哲学の伝統ではないのだ。
|